

上信越自動車道「東部湯の丸IC」を降りてすぐのところに「雷電くるみの里」という道の駅があります。「雷電」は地元東御市出身の江戸時代の力士、「くるみの里」は東御市が日本のクルミ生産量の4割を占める日本一のクルミの生産地であることから双方合わせた駅名になっています。
さて、東御市はなぜクルミの生産量がそれほど多いのか?そんな疑問を以前から思っていたところ、東御市が運営している「サンファームとうみ」でクルミの収穫体験の様子を紹介したニュースがありました。クルミは10月上旬に収穫し周りの果肉を取ってから1ヶ月ほど自然乾燥させて出荷になります。昔は自宅で採れたクルミを天日干ししている家もありましたが最近ではほとんど見られなくなりました。
今なら懐かしいクルミの天日干しの風景が見られるかもしれないし、東御市がクルミ生産日本一の理由も聞けると思い「サンファームとうみ」を訪ねてみることにしました。

「東部湯の丸IC」を降りてバイパスから山に向かって坂道を暫く走ると建物が見えてきます。ここではクルミの品種改良と栽培技術の開発、新規就農者の研修の場としての活用、またクルミ生産者への苗木の供給などの営農支援も行っています。
一般公開している施設ではないのですが技術指導員の平井さんが快く案内してくれました。クルミは透明なビニールハウスの中に日が当たる様に並べられ、扇風機も使って自然乾燥されていました。
ここで栽培されているのは「信濃くるみ」という品種で東洋種のカシグルミと欧米種のペルシャグルミの自然交配種で、大粒ながら殻が薄いので割りやすいのが特長とのことでした。
なぜ東御市が日本一のクルミの生産地になったのか尋ねると次のような説明を頂きました。
クルミの栽培が盛んになったのは大正4年大正天皇即位御大典記念として東御市の旧和村の全戸にクルミの苗が配布され栽培が奨励されました。その後もクルミの将来に希望を抱いた人たちが増産に努め、県の技術指導もあって日本一の生産地になりました。
また、クルミは日当たりが良くて水はけのよい土地を好むのでこの地との相性も良かった事も増産に繋がる大きな一因でした。確かに東御市はリンゴやブドウなどの果実栽培が盛んな地域で特に最近は沢山のワイナリーもできています。
この他、長野県は製糸業が盛んだったので桑を栽培していた農家が沢山ありましたが、昭和に入って製糸業が廃れてしまうと価格が上がっていたクルミの栽培に転嫁していったとの事でした。

そんな話をしながら「食べてみて」と言って乾燥中のクルミを手に取って地面のコンクリートの部分を軽く叩くと殻はすぐに割れました。
食べてみると一般的にナッツ類として売られているものとは風味が全く違います。
「昔食べたクルミの味がします」と言うと、自然乾燥したものは2年位は生きているので酸化が遅いから美味しいけれど火力乾燥したクルミはすぐ酸化して風味がなくなると教えてくれました。

国内で流通しているむきクルミの99%が輸入品で火力乾燥されているものが多いからどうしても風味が落ちてしまう。 自然乾燥している国内産のクルミは貴重で東御市ほどの生産地は国内にはないのでどんどんPRしてほしいと言って「信濃くるみの栽培指針」という冊子を持たせてくれました。
親切に説明頂いたお礼を言い、帰りに建物の裏手に広がるクルミ畑をひと回りしてみました。
クルミの木は大きくなるので鬱蒼としているのかなと思いましたが、木の内部が日影にならないようにすっきりと剪定されていました。また、収穫時は実を下に落とすので地面も綺麗に刈り込まれていて良いクルミを育てるには随分手入れが必要なのだなと思いました。

クルミの話を聞いたところで、さっそく「雷電くるみの里」に寄ってみると農産物直売所にはネットに入った東御市産クルミが置かれていました。大粒で立派なクルミでけっこういい値段ですが、苗から成木になるまでには6年~8年掛かり、出荷に至るまでにも手間が掛かっています。さらに国産品は美味しい分、高価になるのは納得のいくところです。
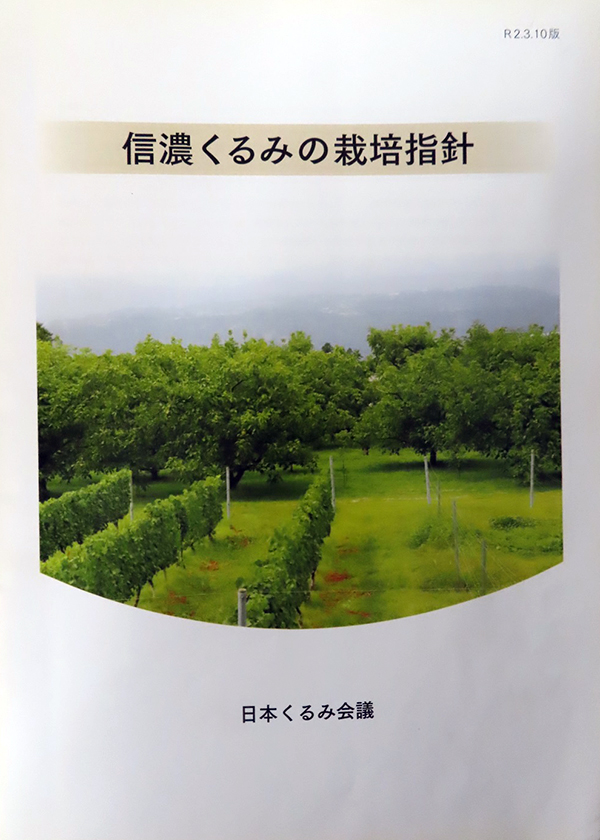
クルミは栄養豊富でオメガ3脂肪酸、ポリフェノールがナッツ類の中で一番多く、最近では認知機能低下予防にも良いという話もあります。 「信濃くるみの栽培の指針」によれば1日一つかみ(30g)の摂取が健康維持に効果的 とありました。そんな量はとても買えないですがせっかく来たので食事処でクルミ蕎麦を食べることにしました。クルミとそばつゆがよく合ってとても美味しいです。また蕎麦の他に「クルミおはぎ」もあってこちらも人気のようでした。
前出の平井さんはクルミは新しいほど美味しいという事でしたので、新物が出荷されているこの時期、信州においでの際はクルミ蕎麦のあるお店を訪ねてはいかがでしょうか。